| Top > 授業 > Delphi プログラミング >限界質量モデル 限界質量モデルについて(2004/11/14) |
| Top > 授業 > Delphi プログラミング >限界質量モデル 限界質量モデルについて(2004/11/14) |
まず何を考えたかですが…。 限界質量モデルで想定する個人の態度、つまり「周囲の人の何%が〜をすれば自分もする」という態度を、調査項目に入れることを考えました。限界質量モデルでは「何%が〜なら」という反応曲線を勝手に仮定しているけれど、実際に測定するとどうなのよ、ということです。 まず、そのようなデータが得られれば、どこに均衡点が来るか、というのが直接的な興味です。 次に、Social Impact 理論のシミュレーションのような状況、つまりセル空間を仮定したモデルで、調査データで得られた度数分布を確率分布と仮定して行為者(セル)の反応を定義した場合、結果がどうなるか、が興味の対象です。オリジナルの限界質量モデルでは、現象に「局所性」がない。つまり集団全体が均質的で、各行為者は全体から影響を受けると考えている。しかし Social Impact シミュレーションのように、行為者は近傍を見て判断するとすると、オリジナルのモデルとは異なった結果になるのではないか? 第1に、「〜をする」人がクラスタをなして存在することになるだろう。第2に、全体の採用率もオリジナルモデルと異なる可能性がある。増えるのか減るのか? |
7月に行った卒論用の調査では、限界質量モデルにそのまま適用することを想定して次の項目を入れていました。今から考えると反省すべき点も多々ありますけど。 Q5.いま仮に、あなたが観ていないテレビ番組をあなたの周囲の人が観ていると分かったとします。このとき、次の(1)と(2)にお答えください。 (1)あなたの周囲の人の何パーセント以上の人が観ていれば自分も観てみようと思いますか? _____% 以上ならその番組を観てみる (2)もし、あなたの周囲の人の多くが観ていれば自分は観ないということがあれば、何パーセント以上なら自分は観ないかをお答えください。思いつかなければ記入しないで構いません。 _____% 以上ならその番組を観ない Q6.いま仮に、あなたが身につけたことがないスタイルの服装を周囲の人(同性)が着始めたとします。そのスタイルの服装は自分でも良いと思うとします。このとき、次の(1)と(2)にお答えください。 (1)あなたの周囲の人の何パーセント以上の人がその服装を取り入れていれば自分も着てみようと思いますか? _____% 以上ならそのスタイルの服装をしてみる (2)もし、あなたの周囲の人の多くがその服装をしていれば自分は着ないということがあれば、何パーセント以上なら自分は着ないかを、お答えください。思いつかなければ記入しないで構いません。 _____% 以上ならそのスタイルの服装をしない 上記の質問項目のミソは(2)を入れたことです。つまり、人間は「みんなと一緒じゃ嫌だ」ということもある。ユニークネスを求めるとでも言いますか。この点を考慮すると、限界質量モデルの反応曲線も単調増加ではなくなるかも知れない。 |
調査データを反応曲線にして、限界質量モデルを適用するプログラムは次でダウンロードできます。 実行プログラム Delphi のソースコード 何れの場合も、cmass.txt というテキストファイルを、実行型ファイル(exeファイル)ないし Delphi のファイルと同じフォルダに入れて実行してください。cmass.txt は上記の調査項目への回答データが入っています。 プログラムは、'Curve' ボタンで反応曲線を描きます。次に 'Sim' ボタンをクリックすると乱数で決めた比率(%)から出発して、限界質量モデルに従った行き着き先を求めます。 |
実際にデータをとって反応曲線を描いてみると、テキスト通りには行きませんなぁ。まず、下図がテレビ番組に関する質問項目を用いた反応曲線です。青い斜めの線が45度直線、赤い線が反応曲線、緑の線は「テレビ番組を見る比率の推移」を表します。 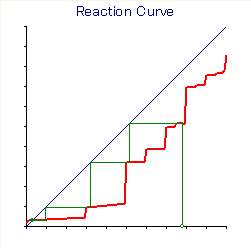 この反応曲線、最初の方を除いて、終始45度線の下に来ます。交点は左下の「3%」のところです。結局、この1点しか均衡点はありません。どこから出発しても3%で落ち着くことになります。 このデータからすると、テレビ番組は他人が観るかどうかにはあまり影響をされない、ということです。テレビ番組は「人が観るから自分も観よう」ということではなく、「自分が面白ければ観る、それだけよ」ということなんでしょうね。 |
同様の反応曲線を服装についてとってみると、次のようになります。 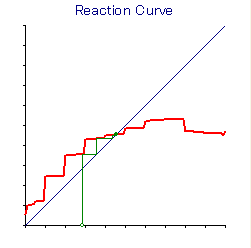 服装の場合、テレビ番組と比べると他人の影響を受けている、ということのように思います。ただ、みんなその服装をすると自分は止める、という傾向も働くので、反応曲線は右側であまり高くならない(むしろ低下してくる)。結局、この場合も45度直線と反応曲線の交点(=均衡点)は1つで、ちょうど45%です。どこから出発しても45%で落ち着きます。 |
ここから先は、Social Impact シミュレーションのやり方の中に限界質量モデルとこのデータを移植することになります。もう少し待ってください。 |