| Top > 授業 > Delphi プログラミング >続・限界質量モデル 続・限界質量モデル(2004/12/03) |
| Top > 授業 > Delphi プログラミング >続・限界質量モデル 続・限界質量モデル(2004/12/03) |
さて、1つ前のページでは限界質量モデルの反応曲線を、質問紙データから推測する、ということをしてみた。今度は、このデータを Social Impact シミュレーションの枠組みに適用してみることを考える。 限界質量モデルというのは、Social Impact 理論(あるいは DSIT)から考えると、影響力が大域的である場合に該当する。ある行動様式を採用している人の比率が全員に知れ渡っている、という場合を考えているからである。しかし人は距離のある空間にいると考えてみよう。そして「近隣」の他者の比率によって反応すると考えてみよう。このとき、人に影響を及ぼすのは局所的な行動の採用率である。このような前提の下では何が起こるか? DSIT のシミュレーションでは、概して、エージェントが局所的影響の場にいるときほど少数派は生き残りやすく、、大域的な影響が及ぶときほど多数派が全体を制圧しやすい。だからこの結果から類推すると、限界質量モデルで均衡解がある行動をとる者が少数派であると予測されるとき、Social Impact 風に影響力を局所的とすれば少数派が生き残りやすくなるのではないか? そのように当初は考えた。 結果は以下である。 |
限界質量モデルに Social Impact シミュレーションの定式化を移植してみる。エージェントは50×50のセル空間にいるとしよう。空間は torus で、上下左右がつながっている。距離はブロック距離で定義してみる(ユークリッド距離でも本質的には結果は同じである)。「近隣」は、ブロク距離1、2、3…のセルだと考える。エージェント=セルは、その近隣における行動の採用比率に反応して、その行動をするかどうかを決めると考える。 調査データは、有効回答数がTV番組で230、服装に関して249である。しかるに、モデルのセル数は2500である。このセルの反応をどのように定義するか。次の方法に従った。まずセルをランダムに並べ替える並べ替えた順番に従ってセルを取り出し、回答者の反応(閾値)を、回答者番号の順にそのセルに割り当てる。最後の回答者の値を割り当てると、また最初の回答者に戻る。回答者が230なら、この操作で、同じ回答者の値は10個のセルに割り当てたことになる。残った200のセルに対して、回答者の中から200をランダムに選び、それぞれの回答者の値を割り当てる。この方法で、すべての回答者の反応はほぼ同数のセルに割り当てたことになる。この操作の後に、セルの番号をもとに戻す。 シミュレーションのプログラム(デモ版)では、RadioGroup で、1つのRunのラウンド数、近隣の範囲を示す距離、初期の行動の採用率、を選べるようにした。次でプログラムをダウンロードできる。 実行プログラム Delphi のソースコード なお、プログラムを実行するには、cm_tv.txt と cm_cos.txt のテータファイルを、exe ファイルないし Delphi ファイルと同じフォルダに入れておく必要がある。 実行してみたら意外とつまらない結果だった。以下で述べる。 |
TV番組のデータに限界質量モデルを適用すると、あるTV番組を観る者の比率は3%で終わる、というのが限界質量モデルの結果だった。実行結果(デモ版)は次のごとく。要するに結果は限界質量モデルと同じく、何度実行しても3%程度の採用率で終わる。残っているのは、他人にかかわらず「自分はその番組を観る」と決めているエージェントである。 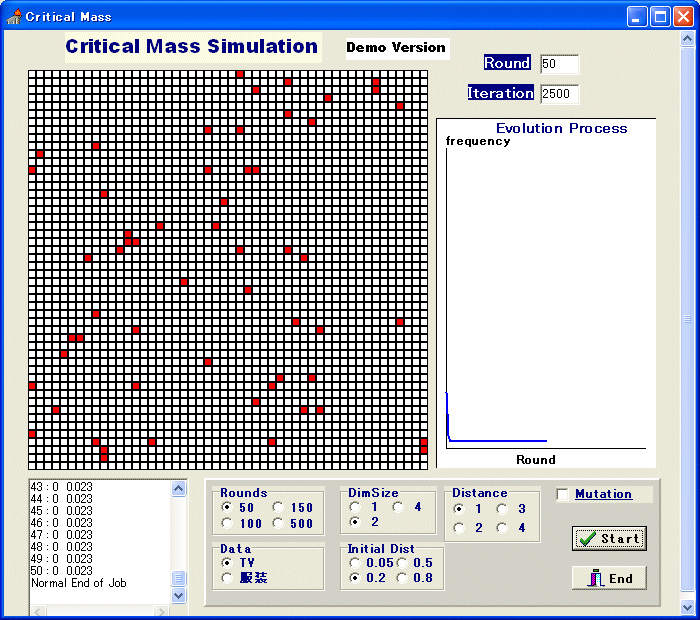 |
服装のデータでは、限界質量モデルは45%の採用率を予測する。Social Impact 風モデルの適用結果は次だった。 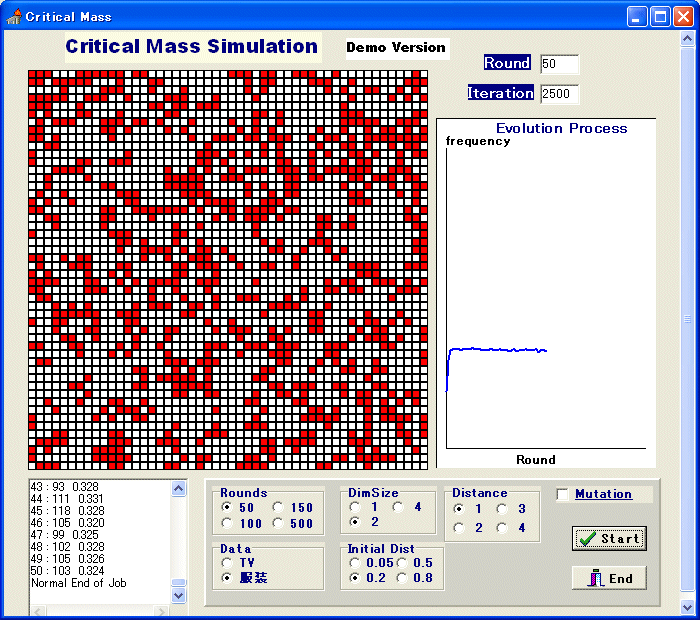 上の結果は近隣を距離1で定義し、初期採用率20%を仮定したときの結果である。最終的に32%程度で終わったから、限界質量モデルの予測よりも採用率は低い。 パラメータをいじって次のことに気が付いた。第1に、距離を大きくすると採用率は限界質量モデルの45%に次第に近づく。距離を際限なく大きくするとこのモデルは限界質量モデルと一致するはずだから、距離を小さくするこ(影響を局所的にする)ことの効果は、一様に採用率を低下させることである。第2に、初期採用率が高い方が、最終的な採用率も高い。この点は限界質量モデルの予測からは逸脱している。 TV番組の結果は、採用率の数字自体が小さいので分かり難いけれど、数字の出方はこの服装の結果と同じだと思う。 |
予想は外れた。ここで用いたデータからすると、影響力を局所的にすると採用する者(この場合少数派)は小さくなる。Social Impact シミュレーションと逆である。影響力の範囲が大域的であるほど、結果はある意味理屈通り、結果は限界質量モデルの予測に近づく。 この結果はデモ版の試行を経ただけであり、ちゃんと繰り返し試行で確認しないといけない。しかし結論は変わらないだろう。 なぜこうなったのか? まず、限界質量モデルと Social Impact とは、発想が異なることを考えないと行けなかったのだろう。Social Impact 理論は、「採用している」も「採用していない」も、ともに同調圧力を発すると考える。しかし限界質量モデルは、「採用していない」エージェントは固有の影響力は発していない、と考えるべきかも知れない。 用いたのとは別の反応曲線を仮定しても同じ結果になるかどうかは、別途検討しないといけない。 この結果を額面通り受け取るとすると、限界質量モデルの前提を Social Impact の定式に組み込むとき、エージェント間の付き合いが広範囲になるほど、ある種の「流行現象」が生じやすいことになる。この結果は、それはそれで意味があるのかもしれない。 |