| Top > 授業 > Delphi プログラミング >限界質量モデル 限界質量モデル:追加調査(2004/12/21) |
| Top > 授業 > Delphi プログラミング >限界質量モデル 限界質量モデル:追加調査(2004/12/21) |
先の記載で、限界質量モデルのための質問紙データをとった次第を説明しました。さらに追加で同様のデータをとることを考えました。第1に、以前のデータには質問文にまずい点があって、改善したいと思った。どう改善したかは、以下の新しい質問文の形式を見て頂けば分かると思います。第2に、前回は「テレビ番組」と「服装」で均衡点がどうなるかを調べようとしたのですが、今回は別のトピックにしてみた。トピックによって結果が異なるものかどうか、というのが注目点です。 |
以下に質問紙の全文を載せておきます。なお、回答者総数は93名です(後期の授業は教養学部の学生だけで、受講者が少ないです)。 ------------------------ アンケートのお願い 時間があれば以下の質問にご回答ください。以下の質問への回答はある4年生の卒業論文のデータになる予定です。よろしくお願いします。 Q1.いま仮に,あなたがある程度人通りの多い歩道を歩いており,あなたの周りには,歩きながらゴミくずを捨てている(ポイ捨て)人がいるとします。このとき,次の(1) ,(2)にお答え下さい。 【注意】:Q2以降も同様です。 (2)もし,あなたの周囲の人の多くが捨てていたら逆に自分は捨てない,ということがあれば,何パーセント以上なら捨てないかお答え下さい。思いつかなければ記入しないで構いません。 【注意】:Q2以降も同様です。 Q2.いま仮に,あなたは赤信号のため道路の横断を待っているときに,あなたの周りには信号を無視して渡っている人がいるとします。このとき,次の(1),(2)にお答え下さい。 (2)もし,あなたの周囲の人の多くが赤信号で渡っていたら逆に自分は渡らない,ということがあれば,何パーセント以上なら渡らないかお答え下さい。思いつかなければ記入しないで構いません。 Q3.いま仮に,あなたが観ていない映画を,あなたの周囲の人が観ていると分かったとします。このとき,次の(1) ,(2)にお答え下さい。 (2)あなたの周囲の人の多くが観ていたら逆に自分は観ない,ということがあれば,何パーセント以上なら観ないかお答え下さい。思いつかなければ記入しないで構いません。 Q4.いま仮に,あなたがまだ読んだことのない本(コミックを含む)をあなたの周囲の人が読んでいると分かったとします。このとき,次の(1),(2)にお答えください。 (2)あなたの周囲の人の多くが読んでいたら逆に自分は読まない,ということがあれば,何パーセント以上なら読まないかお答え下さい。思いつかなければ記入しないで構いません。 ご協力有難うございました。 |
調査データを反応曲線にして、限界質量モデルを適用するプログラムは次でダウンロードできます。このプログラムは先に作ったものと基本的に同じです。 実行プログラム Delphi のソースコード 何れの場合も、cmass2.txt というテキストファイルを、実行型ファイル(exeファイル)ないし Delphi のファイルと同じフォルダに入れて実行してください。cmass2.txt は上記の調査項目への回答データが入っています。 プログラムは、'Curve' ボタンで反応曲線を描きます。次に 'Sim' ボタンをクリックすると乱数で決めた比率(%)から出発して、限界質量モデルに従った行き着き先を求めます。 |
さあて、注目のポイ捨てですが…。 赤い線が質問紙への回答93名分を集計して求めた反応曲線。青い斜めの線が45度直線、緑の線は「ポイ捨てする人の比率の推移」を表します。 結果は「あーあ」という感じ。均衡点は「ポイ捨て率2%」です。つまり「絶対捨てる」人が2%(2人か?)いただけ。「絶対に捨てない」と回答した比率が高いんですわ。social desirability によるバイアスがあるとも考えられます。が、実際、埼玉大学内ではポイ捨てと思えるようなゴミはほとんどないですから、これが真実かぁ、と納得してしまいます。 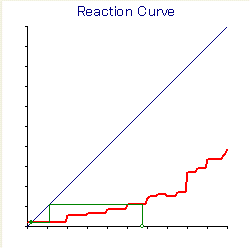 |
同様の反応曲線(93名分)を「赤信号でも渡る」についてとってみると、次のようになります。 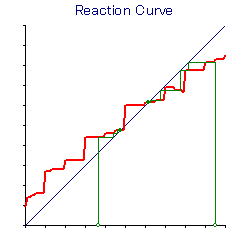 この場合、多分に偶然的要素によると思いますが、反応曲線が45度線に沿っているために、交点=均衡点が2つになりました。計6つのトピックでやって見ましたが、他の5つでは交点はすべて1つであり、この「赤信号」だけが交点が2つ、47%と61%になります。つまり出発点によって行き着く比率が異なります。 |
ついでに「映画」と「本」についての結果は次の図のごとくです。この2つについては「無回答」があるために、それぞれ、回答者は86名と89名でした。結果は先の「テレビ番組」に関する結果と似ています。均衡点はそれぞれ、8%と11%です。他の人の行動分布がそれなりに影響を与えているのですが(ポイ捨ての場合に比べれば)、絶対に採用する人、あるいは低い採用率でも影響を受ける人が少ないために、やはり低い点が均衡点になってしまう。 【映画】 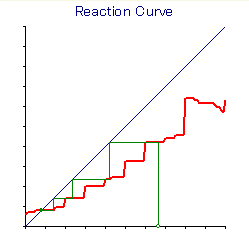 【本】 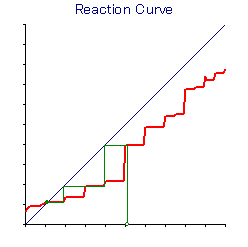 |
最初の質問紙調査では「テレビ番組」と「服装」、ここで書いた追加データでは「ポイ捨て」、「赤信号」、「映画」、「本」でデータを取ってみました。この質問紙調査の結果が信用できる、と仮定しての話ですが、この6つのトピックで現れた反応曲線のパタンは次の3つだったように思います。 1.ポイ捨て:全般に、そもそも「やらない」 2.TV、映画、本:やる人が増えればやる傾向は増すけれども、やる人がよほど多くないと影響を受ける人は少ない。結果として個人主義が支配する。 3.服装、赤信号:0%でもやる人、ないし低い%があればやる人が多い。ただし絶対にやらない人が多く、やる人は大多数とはならない。 ここまでの結果の含意?は次のようなことでしょうか? ①「テキスト通りの反応曲線」、というのは結局、なかったですね。世の中そう甘くない、ということ。この結果で出た反応曲線は、面白みがない分、現実的のような気がします。 ②結果として生じる(であろう)採用率が似たようなものでも、反応曲線で考えるとだいぶ異なるものがありそうに思えます。例えば、「0%でも採用する」という率が低いと、他の人の分布に影響を受ける程度が高くても、45度線より反応曲線が低くなれば、同じような採用率で終わってしまう。ただそれでも、人の反応が同じであるという訳ではない。 ③ある行動を人々に採用させる、という政策的観点に立ったとき、説得して「0%でもやる」人を増やすことはもちろん大事なのですが、「少ない%でも採用するようになる」ような言い方をする、ということも重要になりますね。例えば「頑張っている人に協力しよう、見捨てるな」みたいな。 ④限界質量モデルは、たぶんですが、「やる」/「控える」のどちらを反応と考えてもよいのだろうと思います。質問紙では例えば、「ポイ捨てを何%ならあなたはするか?」と聴きましたが、「40%以上ならする」は「控える人が60%より大なら自分も控える」と読み換えることができる。この点は理屈の上だけの話で、framing が異なるから現実には同じ数字にはならないと思います。framing を変えるとどうなるか、別々に測定するのも手かも知れませんね。 ⑤次の点はボヤッと考えているだけです。Andreas Flache という有能な数理社会学者がいて(Dilemma conference によく来る人)、彼の議論は集団凝集性の double edge ということ。凝集性が高いと social control が効く、つまりみんなで良いことをする可能性もあるけれど、条件によってはみんなでサボることも多くなる、という話があった(ような気がする)。これと(理屈は異なりますが結果として)関係あるかなぁ、と思うことがあります。つまり、凝集性が高い集団/社会だと、人は規範(=多数派)への反応傾向が高まる。ある行動を採用する比率を軸にとるとして、反応曲線で描けば、全体の採用率の低いときには曲線は低迷し、高くなると極端に上がる、そんな反応曲線になるような気がする。つまり、均衡点は両極にぶれることになるのではないか?ということ。もっとも、「採用」が「協力」のように正の外部効果がある場合、「採用する」方向に流れるとは思いますが。 |